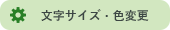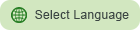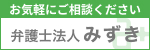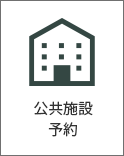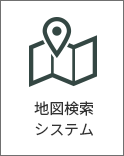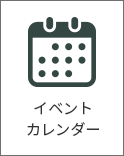児童手当の現況届(令和6年度)
令和4年6月から現況届の提出が原則不要に
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
現況届が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が下野市と異なる方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、下野市から提出の案内があった方
※ 現況届の提出が必要な方で提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※ 現況届に関するQ&Aは、こちらをご覧ください。
現況届の手続(現況届の提出が必要な方)
提出する書類
不備のないようご提出ください。
- 児童手当・特例給付 現況届
※現況届は郵送で送付します。
※同封されている記入例を参考に、必要事項を記入してください。 - 受給者の健康保険証のコピー(国家公務員共済、地方公務員等共済組合に加入している方)
※健康保険証のコピーは、現況届の用紙の裏面にのり等で貼り付けてください。
受給者が児童と別居している場合に提出が必要なもの
上記の 1・2 に加えて下記書類の提出が必要となります。
その他
必要に応じて、追加で書類を提出していただくことがあります。
提出方法
同封の返信用封筒にてご提出ください。提出書類に不備のないようご確認をお願いします。
※窓口での提出も可能ですが、混雑が予想されますので郵送での提出にご協力ください。
提出先
下野市役所
提出期限
令和6年6月28日(令和6年度分)
※提出期限を過ぎた場合、10月に予定している支払いが遅れることがあります。
※提出期限を過ぎた場合でも受付は行っています。ただし、手当を受給する権利は2年間で時効となります。早めにご提出ください。
過年度の現況届の提出について
過年度分の現況届を提出しないまま2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。
下記期日までにご提出がない場合、児童手当を受給することができません。
- 令和4年度現況届は令和6年10月10日まで
- 令和5年度現況届は令和7年10月10日まで
現況届の提出後は
- 提出書類に不足のある方には通知しますので、至急、不足書類を提出してください。すべての提出書類が揃わないと審査が保留となり、手当が支給されません。また、提出が遅れた場合には、10月に予定している支払いが遅れることがあります。
- 現況届の審査には概ね2~3か月かかるため、提出の有無・審査結果などのお問い合わせには、審査が終了するまで回答できない場合があります。
- 審査の結果、受給要件を満たし、継続して6月分以降の手当を受給される方への通知はありません。ただし、下記の場合には通知を発送します。
- 所得の審査の結果、5月分までの手当額と6月分以降の手当額に変更のある方には、認定通知書を送付します。
- 所得の審査の結果、配偶者の所得が高く所得制限限度額以上であった場合には、受給者の変更手続(今までの受給者から配偶者への変更手続)が必要となります。消滅通知と受給者変更に必要な書類を送付します。
児童手当・特例給付の所得上限について
令和6年6月分から令和5年中の所得で審査します。令和4年中の所得が特例給付の所得上限限度額を超えていた方で、令和5年中の所得が所得上限限度額を下回った場合は、認定請求書を提出することで、児童手当・特例給付を受給することができます。手当額や支給については、こちらをご覧ください。
市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。
| 所得上限限度額 | ||
|---|---|---|
|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 |
収入額の目安 |
|
0人 (前年末に児童が生まれ ていない場合等) |
858万円 | 1,071万円 |
|
1人 (児童1人の場合等) |
896万円 | 1,124万円 |
|
2人 (児童1人+収入103万円 以下の配偶者の場合等) |
934万円 | 1,162万円 |
|
3人 (児童2人+収入103万円 以下の配偶者の場合等) |
972万円 | 1,200万円 |
|
4人 (児童3人+収入103万円 以下の配偶者の場合等) |
1,010万円 | 1,238万円 |
|
5人 (児童4人+収入103万円 以下の配偶者の場合等) |
1,048万円 | 1,276万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。